

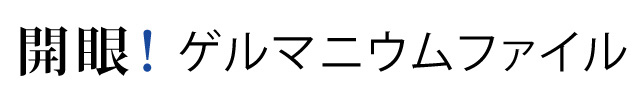
2020.12.17
浅井一彦博士のアサイゲルマニウムが石炭の研究をきっかけに創製されたことは何度かご紹介しました。石炭からもゲルマニウムが抽出されます。石炭のもとは植物です。ということは…植物とゲルマニウムは何やら関係がありそうです。
ゲルマニウムの半導体としての性質が発見されて以来、原料資源の活発な探査が始まり、現在では亜鉛や銅などの鉱石から採取する方法と、石炭から採取する方法とがあります。石炭は地殻活動により空気を遮断した高圧高熱化状態で植物が炭化してできたものです。なぜ石炭にゲルマニウムが含まれるのかについては、「由来植物にもともと存在した」とか「石炭生成後、土壌中のゲルマニウムが濃縮された」など、国内外で様々な主張がありました。(財)石炭総合研究所所長だった浅井一彦博士は、大量の各種石炭の顕微鏡観察と化学分析を行い、「植物の炭化過程で土壌内から石炭に移るのではなく、石炭を形成する植物の生存中からそこに存在する」という結論を導き、発表しましたが、この主張に対しては多くの研究者間で大論争が行われました。
ところで、ゲルマニウムという元素は炭素やケイ素と同じ14属の元素ですが、半導体としての性質を持つことを含めて特にケイ素とよく似た化学的性質を持っています。そのため地球上でケイ素が存在するほとんどのところにゲルマニウムも存在しますが、その量は、地球の表層(地殻)を一番多く占める酸素に次いで2番目に多いケイ素に対し、ゲルマニウムはケイ素の約0.0025%しかありません。でもゲルマニウムが特別少ないかといえばそうでもなく、スズや鉛などより多く、銀よりははるかに多く存在しているのです。
地球が生まれ、やがて海ができたとき、原岩石から河川に溶け出したケイ素やゲルマニウムは海に流れ込み、多数の珪藻植物やプランクトン等に摂取されました。これらの生物に含まれるケイ素とゲルマニウムは陸地岩石中と濃度比が驚くほど一致していて、ケイ素とゲルマニウムがどこまでも共に行動していることがわかります。
地殻の多くを占めるケイ素は土壌中から根を通して吸収されるため、ほとんどの植物中に含まれています。中でもイネ科の植物には多量のケイ素が含まれることが知られています。イネ科植物が細くても丈夫なのは、茎内でケイ素が壁や節の組織の一部となってその強さを増すことに貢献しているからで、植物にとって必要な元素といえるのです。もちろんケイ素と行動を共にするゲルマニウムも量がわずかとはいえどんな植物中にも分布しています。
浅井博士は、文献によりその節ふしにケイ素が、ひいてはゲルマニウムが多く存在すると思われる竹を日本中から採取収集してゲルマニウム量を測定したところ、数種類の笹に15~20ppm もの濃度のゲルマニウムが含まれていました。ちなみに通常、地殻に存在するゲルマニウムは1~2ppm 程度とされています。他の植物でも茶の新芽、カシワの葉などに10ppm 近いゲルマニウムが発見され、浅井博士は当時、ゲルマニウムが植物の光合成に関与している可能性を示唆しています。また、漢方に使われる植物についても、他の植物に比べ高値を示すものが多かったことを報告しており、浅井博士はこれらの植物は外敵から身を守る手段としてゲルマニウムを役立てたのではないかと推察していました。

半導体原料としての用途開発が行き詰っていた1955年頃、炭研では研究材料であるゲルマニウムが身近にあったこともあり、ゲルマニウム化合物の研究を開始していました。浅井博士はそれまでの研究から、石炭にゲルマニウムが多く含まれていることの意味を、石炭の素となる植物が生育生長していくために必要なものとして吸収していたのではないかと強く考えていました。更に当時ヨーロッパではゲルマニウムの医薬への応用研究が進みつつあることを知り、生理活性のあるゲルマニウム化合物についての研究が浅井博士率いる炭研の中心テーマとなっていったのです。
彼らは、「二酸化ゲルマニウム果糖液を用いたX線による放射線障害に対する治療及び予防効果」についての動物実験では一定の成果を得ていました。しかし、二酸化ゲルマニウムによって実験中にマウスが死亡していくことから無機ゲルマニウムでの研究に限界を感じ、安全で生理活性のある有機ゲルマニウム化合物合成への遠い道のりを歩み始めたのでした。
そして1966年、ついに安全で生理活性を持つ水溶性の有機ゲルマニウム、すなわち『アサイゲルマニウム』が創り出されたのです。半導体開発から一転、わずかな情報とわずかな実験結果、厳しい財政状況にもかかわらず、ゲルマニウムに対する先見性と強い思いから、有機ゲルマニウムの開発にこだわった浅井博士の無謀な挑戦は、井深氏に通じるものがあったかもしれません。
半導体原料としてスタートしたゲルマニウム研究が、18年後にはアサイゲルマニウム創製につながり、そして㈱浅井ゲルマニウム研究所に引き継がれ、浅井博士の信念と願いの結晶であるアサイゲルマニウムの新たな可能性を探る挑戦が、今も続けられているのです。
半導体原料としての用途開発が行き詰っていた1955年頃、炭研では研究材料であるゲルマニウムが身近にあったこともあり、ゲルマニウム化合物の研究を開始していました。浅井博士はそれまでの研究から、石炭にゲルマニウムが多く含まれていることの意味を、石炭の素となる植物が生育生長していくために必要なものとして吸収していたのではないかと強く考えていました。更に当時ヨーロッパではゲルマニウムの医薬への応用研究が進みつつあることを知り、生理活性のあるゲルマニウム化合物についての研究が浅井博士率いる炭研の中心テーマとなっていったのです。
彼らは、「二酸化ゲルマニウム果糖液を用いたX線による放射線障害に対する治療及び予防効果」についての動物実験では一定の成果を得ていました。しかし、二酸化ゲルマニウムによって実験中にマウスが死亡していくことから無機ゲルマニウムでの研究に限界を感じ、安全で生理活性のある有機ゲルマニウム化合物合成への遠い道のりを歩み始めたのでした。
そして1966年、ついに安全で生理活性を持つ水溶性の有機ゲルマニウム、すなわち『アサイゲルマニウム』が創り出されたのです。半導体開発から一転、わずかな情報とわずかな実験結果、厳しい財政状況にもかかわらず、ゲルマニウムに対する先見性と強い思いから、有機ゲルマニウムの開発にこだわった浅井博士の無謀な挑戦は、井深氏に通じるものがあったかもしれません。
半導体原料としてスタートしたゲルマニウム研究が、18年後にはアサイゲルマニウム創製につながり、そして㈱浅井ゲルマニウム研究所に引き継がれ、浅井博士の信念と願いの結晶であるアサイゲルマニウムの新たな可能性を探る挑戦が、今も続けられているのです。